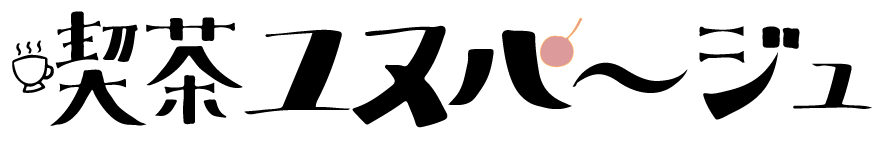達者な技術に裏打ちされたギタリストとしての矜持と、曲のアウトラインを曖昧にする中性的な声……君島大空という音楽家の柱になっているのは間違いなくその2点と言っていい。そして、それが自在なクラフツマンシップに基づくものであることも、このファースト・フル・アルバムの12曲から感じ取ることができる。
例えば、さりげなくコードを動かしていくことで曲に儚さや白眉さをもたらす曲を作らせたら本当にうまい。2021年に最初にシングルとして発表され、本作にも収録された「光暈(halo)」という曲。最後の歌詞部分“飲み込む/波浪/打ち寄せる/光暈”の、“寄せる”から“光暈”へと移るコード進行(Fmaj7→A#maj7か?)はかなり繊細だ。聴いたことのない斬新なコード進行を求めた末の突飛なトライではなく、ギターの音の揺れや自身の声の揺らぎとの相乗効果で自然と(あるいは仕方なく)こうした展開を好むようになったのだろうか。「シャウトしたくてもできないから低音の薄い音作りになった」というエリオット・スミスのエピソードを思い出す。
だが、君島は徐々にバンド・セットでライヴを行うようになった。最近のEPがそうだったように本作もドラム/パーカッションで石若駿、ベースで新井和輝(キング・ヌー)、ギターで西田修大らが参加。「光暈」もその石若、新井との3ピースで新録されていて、昨年ピノ・パラディーノと来日し、サム・ゲンデルらとステージに立ったブレイク・ミルズの開かれたセッションがほんの少し頭をよぎる。繊細なギターと歌を纏ったさりげないコード進行に心が持っていかれる……のはもちろんそうだが、そうした細部以上にアンサンブルの旨味で楽しめる曲が増えているのは大きな変化だ。同タイプの曲としては「19℃」もそう。このあたりは、彼自身交流ある岡田拓郎がバンドで演奏し、自ら歌った時とやや通じるものがある。
ただし、岡田が最新作で歌から遠ざかったのとは対照的に、君島は本作で割と素直に自身のメロディーに声を寄り添わせている。彼の書く旋律は古典的な日本のフォークやニュー・ミュージックの系譜上にあるため、ドラム、ベース、ギターという普遍的なバンド・アンサンブルの上に乗った時にいい意味でわかりやすいロック/ポップスとしても聴けるようになる。その象徴が「都合」や「No heavenly」だ。くるりやフジファブリックが継承してきたような日本産フォークへの理解のある和製オルタナティヴ・ロックに転じていくスリルたるや……もちろんバッキングは石若、新井、西田らだから演奏自体に野暮ったさはないが、とりわけ「No heavenly」は最終曲なだけに強烈な破壊衝動を残す。ここが本作最大の面白さではないだろうか。様々なスタイルのギターが弾けるギタリストなのにあえて荒削りなロックを聴かせるマーク・リーボウのセラミック・ドッグを思い出す。
そして、轟音になってもヴォーカルの線の細さを全く感じさせないのはミックスのなせる技か。もちろん君島本人によるもの。そうしたコントロールの塩梅も含めて、圧倒的なファースト・アルバムだ。(岡村詩野)
こちらを表示中: